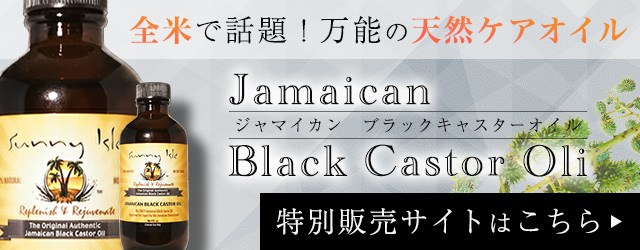はじめに
ウスターソースは、家庭料理や洋食に欠かせない調味料として知られています。
その独特な風味は、多くの料理を引き立てる名脇役ですが、名前の由来については意外と知られていない方も多いのではないでしょうか。
今回は、そんなウスターソースの名前の由来や歴史についてご紹介いたします。
“ウスター”の名はどこから?名前の由来をたどる
ウスターソースの「ウスター」は、イギリス・ウスターシャー州の州都「ウスター市」に由来します。
この地で19世紀後半、インドから帰国したイギリス貴族が薬剤師に製造を依頼したことがきっかけで誕生しました。
元祖となったのは「リー&ペリンズ社」のウスターソースで、現在もイギリスで販売されています。
誕生には諸説あり、一つはインド料理に感銘を受けた貴族がその味を再現したという説。
もう一つは、ウスター市の主婦が余った野菜や果物を保存しておいたところ、熟成されて美味しい液体が生まれたという話です。
イギリス式のウスターソースはモルトビネガーを主原料とし、アンチョビや香辛料を加えて熟成させたため、日本のものより酸味が強くサラッとした液体状です。
この違いが後に日本独自の進化につながります。
日本でのウスターソースの広まりと独自進化
日本には江戸時代末期に渡来し、明治維新後に洋食文化とともに広まりました。
しかし、初期の国産品「ミカドソース」はイギリス式製法だったため、日本人には馴染まず短期間で製造中止となりました。
その後、日本人向けに改良が重ねられ、甘さととろみを加えた独自の味わいへ進化。
明治時代後期〜大正時代には、家庭用商品として普及しました。
さらに昭和になると、お好み焼き向けの「お好みソース」なども開発され、日本ならではのバリエーションが豊富になりました。
ウスターソースと他のソースの違いとは?
日本では「ウスター」「中濃」「濃厚(とんかつ)」など、粘度や風味によって分類されています。
以下はそれぞれの主な特徴です。
ウスターソース
繊維質が少なくサラッとしており、辛味が強め。
中濃ソース
ほどよい粘度で甘味と辛味のバランスが良い。
濃厚ソース(とんかつソース)
果実使用量が多く、とろみが強く甘め。
用途によって使い分けることで料理の仕上がりも変わります。
また、「お好みソース」は濃厚タイプに近い粘度で、お好み焼きや焼きそばに最適です。
まとめ
ウスターソースはイギリス発祥ながら、日本で独自進化を遂げた調味料です。
その名前はイギリス・ウスター市に由来し、日本では洋食文化とともに広まりました。
現在では家庭料理からプロの料理まで幅広く使われており、その種類も豊富です。
ウスターソースの名前の由来や歴史を知ることで、この調味料への理解が深まり、より楽しく料理を楽しめるでしょう。